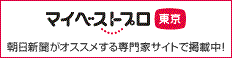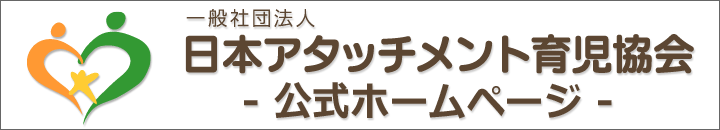過去配信の動画
クラスレッスンオープニングの曲など、過去配信の動画はこちらから
2020/05/07配信
こんにちは😃
親子教室ママンジュのレッスン開始のお歌が変わります❣️
新沢としひこ作詞・作曲『あいさつおぼえうた』の動画をLINEご登録の皆様にはこどもの日に一足先に配信致しました。
ホームページへの掲載はちょっとしたトラブルにより大変遅くなりました!
ごめんなさい💦
YouTube動画を貼りましたのでご視聴頂いたら「いいね」を宜しくお願い致します。m(_ _)m
是非お家で覚えてね。
そして教室再開の時、一緒に歌いましょうね。
★ご注意★
手話を使った歌ですが、決して手話を覚えさせようと思ってやらないで下さい。
簡単な手話であってもまだお子様には難しいです。
★目的と遊び方★
ママ、パパが楽しく歌って見せてあげるが大切。
子供は楽しいことはマネしたくなります。
マネをすると模倣反射が旺盛になり、脳や手、指の発達が促されます。
脳や手指の発達は言葉や思考の発達にも繋がり、今のお子様にとって大変重要❗️
そして、気がつくと手話を覚えてたという嬉しいオマケつきの歌です。
★その他★
最初の部分に手話の紹介が流れます。
紹介部分には音は付いていません。
初めての動画撮りで顔が引きつってますがお許しくださいね
今後も遊びの紹介なども予定してますので、公式LINEへのお友だち登録を宜しくお願い致します!
公式LINEお友だち追加はこちらから
2020/05/16配信
※ Instagramへの配信は動画の上下が切れておりポイント説明が入っておりません。m(_ _)m
紙コップを使った積み木遊び、トンネルくぐりの遊びです!
積み木は手の発達を促すと共に、空間認識力も育てます。
遊び方は発達に合わせた順序を辿ることが大切。
0歳はまずパパママが作る姿を見せて、それを壊すことから遊びが始まります。
【注意】動画は人形のため手を添えてますが、実際はお子様の自由に。
決してお子様を投げて壊したりしないでね。
積み木を「積む」ができるようになったら、ママと一緒に紙コップトンネルを作ってみよう。
トンネルくぐりは、脳が目覚しく発達する6〜7歳頃まではどんどんやってね。
ハイハイ運動は中脳や他の脳の部分を育てます。
お家遊びの一つとして楽しんでみて下さいね!
2020/05/23配信
☆ペットボトル・ストロー・ひも通し☆
☆簡単!穴のあけ方☆
脳が急速に発達してゆく幼児期は
手先をたくさん使った遊びが大切です。
「手は脳である」
哺乳類の中で一番脳が発達したのは人間であり、一番手先を器用に使えるのは人間です。
手を使うことで脳のあらゆる部分と連動して賢い脳へと成長させます。
生まれつき不器用な人はいません。
どれだけ手を使った遊びを行うか!
これが幼児期の脳の成長には大きく関わってきます。
くれぐれも誤飲に注意を払いながら、手先を使う遊びをたくさんやってみてね!
※穴の開け方もあります。
ペットボトルやプラスチックの容器の蓋など、きれいな穴開けが難しい時に試してみてね。
Instagramはこちらから
↓↓↓↓↓↓
https://www.instagram.com/mamangemama
2020/05/25配信
☆手指が育つおやつ探し遊び☆
お菓子の味を知ると
「お菓子ちょうだい!もっとちょうだい!」と、
ママを困らせることありますよね?
ダメダメばかり言いたくないし・・・
そんな時にはこの遊び。
宝探しのような『おやつ探し』!
この遊びの中には急速に脳が発達する乳幼児期に欠かせない手を育てる要素がたっぷり入っています。
お菓子を食べたいという欲求ゆえに、ママが仕掛たお菓子の入れ物を一生懸命開けようと集中して取り組むでしょう。
動画を参考に、ママのアイディアで楽しいおやつ探しを仕掛けてみてね。
【注意】
誤飲にご注意ください。
決して目を離さないでね。
2020/05/26配信
☆いろんなものを比べちゃおう!☆
厚紙・シーソー
(1歳後半~2歳・3歳)
遊びの中で身近なものを比べてみよう。
「重さの概念」を経験として学びます。
どっちが重い?
数の多少では?
大小では?
置く場所では?
シーソーで釣り合う数・大きさ・位置を遊びの経験から知ることで、理科の学習が大好きになることでしょう。